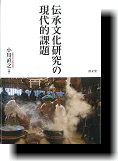 柳田國男は「民間伝承」、折口信夫は「生活の古典」に視座をおき、斬新な論理で描き出した庶民生活史・伝承文学史を、「伝承文化研究」という枠組みで括り直し、そこから現代の研究者がどのような課題と視点で社会や文化を考えようとしているのか、その格闘を伝承文化の「意義と機能」「認識と発見」「継承と変化・変容」「生成と展開」「実践と提言」の5テーマ、14論文で提示する。
柳田國男は「民間伝承」、折口信夫は「生活の古典」に視座をおき、斬新な論理で描き出した庶民生活史・伝承文学史を、「伝承文化研究」という枠組みで括り直し、そこから現代の研究者がどのような課題と視点で社会や文化を考えようとしているのか、その格闘を伝承文化の「意義と機能」「認識と発見」「継承と変化・変容」「生成と展開」「実践と提言」の5テーマ、14論文で提示する。■本書の構成
序 伝承文化研究の現代的課題とは…………小川直之
Ⅰ 意義と機能
魔除け再考 -「結び」と「自我」- …………小川直之
「天真名井」伝承にみる土地人の意識 -地域の特性を知るてがかりとして- …………大館真晴
キツネガリ行事と子ども集団…………服部比呂美
Ⅱ 認識と発見
オモロと琉歌の歌唱法 ―琉歌発生論の再検討― …………狩俣恵一
性に関わる病の伝承 -「南無薬師」歌と流された女- …………佐伯和香子
芸能伝承としての小松市曳山子供歌舞伎…………高久 舞
Ⅲ 継承と変化・変容
民俗文化の変容と継承への視座 -和歌山県での継続調査から- …………藤井弘章
民俗芸能の変容とその要因 -遠山霜月祭を中心に- …………櫻井弘人
釜神祭祀にみる秋山郷の近現代 -釜神起源説話の検討- …………渡邉三四一
Ⅳ 生成と展開
失われた<修験道>を求めて -現代英彦山における修験復興運動について- …………須永 敬
子取り論序説 -妖怪伝承の現代的意味- …………伊藤龍平
火葬の場における文化の伝承とその拡大…………川嶋麗華
Ⅴ 実践と提言
民俗芸能の継承への提言 -民俗芸能研究は今何ができるのか- …………大石泰夫
博物館と民俗学 -市民参加の活動を巡って- …………加藤隆志
あとがき
小川直之(おがわ なおゆき)…………1953年生 國學院大學名誉教授 柳田國男記念伊那民俗学研究所長 博士(民俗学)
編者の関連書籍
小川直之・大石泰夫・服部比呂美・飯倉義之編 伝承文学を学ぶ
本書の関連書籍
野村純一著作集 全九巻
『伝承文化研究の現代的課題』の意図と内容
この視座と目的は現在も変わりないが、本書では、その研究対象を広げる試みの一つとして、「伝承文化研究」という枠組みを提示した。かつて柳田國男は「民間伝承」、折口信夫は「生活の古典」という術語の構築によって、「民俗学」という新たな学問領域を創出した。それが現在の民俗学に受け継がれているが、柳田や折口の研究視座と課題は、必ずしも民間や庶民に限定されるものではなく、「伝承」という継承様態による生活や文化、文学のありようにも置かれていた。こうしたことを踏まえつつ、いわば伝承文化学とでもいえる領域を模索するために編んだのが本書である。
どのような学術分野であろうと、現在に生きる者は、自らが置かれている場や状況のなかで疑問や課題を立ち上げ、それを論理化しながら研究という行為を続ける。疑問や課題の発見、論理化を研究の第一歩とするところに経験科学としての、それぞれの個性と現代性があるといえよう。論集としたのは、その個性と現代性の在り様を示すためである。
本書の意図を端的に述べるとこのようになるが、この意図のもとに収録した十四論文は、伝承文化がもつ意義や機能を論じたもの、伝承文化をどのように認識したり発見したりするのかを論じたもの、伝承文化の継承と変化・変容を論じたもの、伝承文化の生成と展開を論じたもの、伝承文化研究の社会的実践やこの研究をもとにした提言を内容とするものである。これらの視座と研究課題は、単純に切り分けることは出来ず、当然、重層や複合があるが、ひとまず本書ではこれに基づいてⅠからⅤの部立てを設けた。
人類が築いてきた社会や文化は、その多くが「伝承」に拠って継承され、これによって人間としての営みが成り立っているといえよう。こうした伝承文化は広大な領域をもつのであり、本書は、これを捉える視座と課題検証の足場を示すものである。